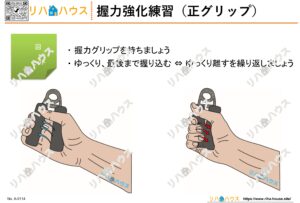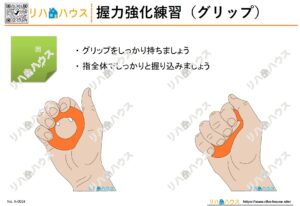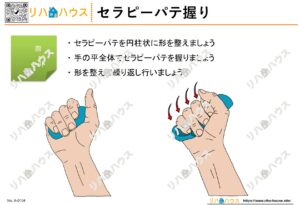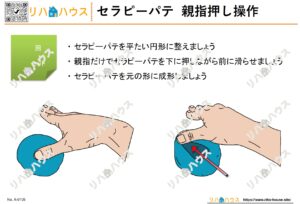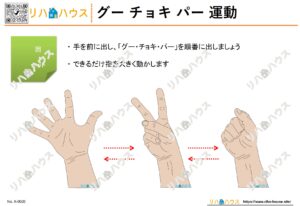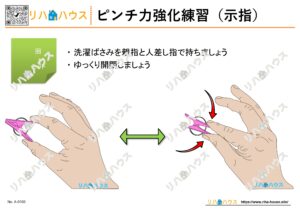このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。
はじめに|側屈ストレッチが必要とされる理由とは?
体幹の柔軟性は、日常生活動作(ADL)や移動動作において極めて重要な役割を果たします。特に側屈動作(左右への体幹の傾き)は、歩行中の体重移動や、衣服の着脱、床からの拾い動作など、細かな活動に密接に関与しています。
今回リハハウスで提供する「体幹の側屈ストレッチ」は、腹斜筋や広背筋、肋間筋、大胸筋、殿筋群などの多関節にわたるストレッチを目的とした素材です。上肢の位置や動作の軌道を工夫することで、腋窩から骨盤までを一連で伸ばす動きが可能となり、全身的な柔軟性向上と関節可動域(ROM)の拡大に寄与します。
※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。
内容と目的|体幹側屈ストレッチで狙うべき解剖学的ターゲット
このストレッチで得られる具体的効果
以下の筋群・関節可動域に対する柔軟性向上が主な目的です
- 関節可動域の拡大
特に、体幹・肩甲帯・上肢・胸郭・脊柱(胸椎〜腰椎)の側屈運動域を拡げることで、動作時の可動性を改善します。
- 筋の伸張による柔軟性向上
外腹斜筋・内腹斜筋・広背筋・肋間筋・大胸筋・上腕三頭筋・大殿筋など、複数部位にまたがる筋を同時にストレッチすることができます。
- バランス能力と姿勢制御の補助
体幹の側屈可動域を維持することで、立位・歩行中の体幹コントロールや転倒予防にも寄与する可能性があります。
- 呼吸機能の改善補助
胸郭の拡張性向上を通じて、肋間筋や大胸筋の伸張が呼吸時の胸郭運動にプラスに働くと考えられます。
このように、多関節・多筋群にアプローチできることが、この素材の特長です。
運動方法と活用方法|上肢と体幹の連動で効果を最大化
実施手順
- 準備姿勢
椅子に腰掛けるか、安定した立位姿勢を取ります。背筋を伸ばして胸を開き、骨盤を正中に保ちます。
- 手の位置をセット
両手を頭の後ろで組み、肘を横に広げます。この姿勢により、上肢から肩甲帯を含む筋群へのテンションが自然にかかります。
- 側屈動作の実施
体幹を左右どちらか一方へゆっくりと倒します。このとき、前方へ屈曲しないように意識し、腋窩〜骨盤の側面が伸びていることを感じながら行うことが大切です。
- 元の姿勢に戻す
ストレッチをかけた側と反対の筋の収縮を意識しながら、体幹を元の位置に戻します。左右交互に、10回×2〜3セットを目安に実施します。
活用シーンの例
- 慢性腰痛・体幹拘縮がある患者への可動域維持ストレッチ
- 脳血管障害後の体幹リハビリ初期段階
- 姿勢改善や呼吸機能の補助を目的とした自主トレ
- 座位・立位バランス能力向上を目指す高齢者向け運動
どの場面でも、ビジュアル付きのプリント素材があることで、説明の明瞭化・運動継続率の向上に役立ちます。
注意点と安全への配慮|患者の体調と理解に応じた実施を
呼吸を止めない
運動中に呼吸を止めると、血圧上昇や筋緊張の増加などリスクを伴う可能性があります。自然な呼吸を維持しながら、ゆっくりと動作を行うように指導しましょう。
前屈しない意識
側屈運動中に体幹が前傾してしまうと、ストレッチの効果が薄れ、腰椎への負担が増加するおそれがあります。「体の真横に倒す」意識を持たせ、肩・骨盤のラインを崩さないようサポートしましょう。
動作は必ずゆっくり
勢いをつけた運動や、反動を使った動作は筋損傷や不適切な動きの原因になります。**「3秒かけて側屈し、3秒かけて戻す」**といったリズムを推奨し、安全性を確保します。
痛みの出現に注意
関節拘縮や神経障害を有する方では、過伸張による疼痛の誘発リスクがあります。実施前には必ずROM評価・疼痛スクリーニングを行いましょう。
まとめ|体幹側屈の柔軟性は全身機能に波及する
「体幹の側屈ストレッチ」は、上肢・体幹・肩甲帯・胸郭など複数の関節・筋群にアプローチ可能な多機能ストレッチです。側屈運動は日常のあらゆる動作に関連しており、この運動の可動性を確保することで、姿勢保持・移動動作・呼吸機能・ADL動作の改善が期待できます。
素材としても汎用性が高く、訪問リハビリ・通所・病棟・外来いずれの場面でも使いやすく、イラスト付きで説明が明確になることから、患者の理解度・継続意欲向上にも有効です。
適切な実施方法と十分な安全配慮を前提に、ぜひ現場でのリハビリテーション指導や自主トレーニング支援にご活用ください。