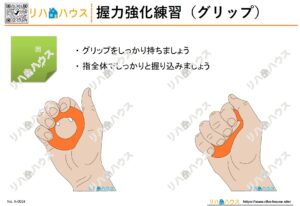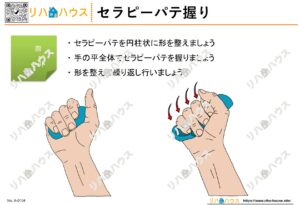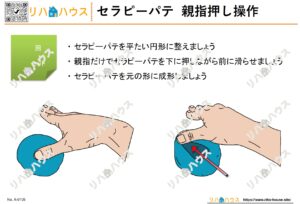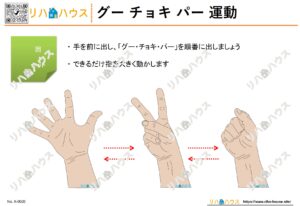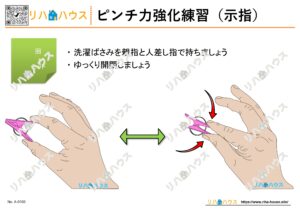このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。
はじめに|「手関節の動き」を取り戻すためにできること
手関節は、私たちが日常生活の中で道具を使ったり、手をついて体を支えたりといった、さまざまな動作を行う上で重要な役割を果たしています。中でも掌屈(てのひらを曲げる)と背屈(手の甲側に反らす)動きは、手の機能を支える基本的な運動軸となります。
今回ご紹介するのは、右手の手関節掌屈・背屈運動に特化した自主トレーニング用イラスト素材です。視覚的に理解しやすく、リハビリ現場での指導だけでなく、対象者自身のセルフトレーニングや家族によるサポートにも活用しやすい内容となっています。
※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。
内容と目的|手関節の機能を支える筋群に働きかける
素材の内容
このプリントでは、右手の手関節掌屈・背屈運動をテーマに、動作の流れや姿勢をイラストでわかりやすく解説しています。すべての手指を伸展した状態で、手関節を正中位(手が真っすぐな状態)から前後にゆっくりと動かす運動を繰り返す形式です。
目的と対象筋群
手関節の掌屈・背屈運動では、以下のような筋群が関与します
- 撓側手根屈筋/尺側手根屈筋:掌屈(手を内側に曲げる)時に働く
- 長橈側手根伸筋/短橈側手根伸筋/尺側手根伸筋:背屈(手を甲側へ反らす)時に働く
これらの筋群を意識的に使うことで、以下の効果が期待されます
- 筋力の維持・強化
- 手関節の柔軟性向上
- 関節可動域の拡大
- 手首周囲の筋バランスの安定化
本素材は、特に手関節の可動性が低下している方や、長時間の固定後に運動再開を検討している方にとって、段階的に導入しやすい設計となっています。
運動方法と活用方法|シンプルで取り組みやすい自主トレーニング
このトレーニングは、特別な道具を使わずにその場で簡単に行えるという点が大きなメリットです。視覚的なガイド付きなので、対象者自身でも安心して取り組むことができます。
実施手順(基本ステップ)
- 椅子に座り、前腕を机や太ももに安定して乗せる
- 手指をまっすぐに伸ばした状態(伸展位)を保つ
- 手首をゆっくりと掌屈方向(手のひら側)へ曲げる
- 次に、背屈方向(手の甲側)へ反らす
- 掌屈と背屈を交互に10〜15回繰り返す
推奨頻度
- 1日2〜3セット程度を目安に無理のない範囲で実施
- 疲労感がある場合はセット数を調整
活用シーン
- 回復期リハビリ病棟での関節運動指導
- 在宅リハでの自主トレ支援資料として
- 訪問リハビリでの家族指導ツール
- 職業復帰支援の初期訓練として
素材はPDF形式で提供されており、印刷してすぐに現場で活用できるようになっています。
注意点と安全への配慮|無理のない範囲で行うことが大切
手関節の運動は、正しいフォームで実施することでより安全かつ効果的に進めることができます。以下の点に注意しながら指導・実践を行いましょう。
注意点
- 急激な動きは避け、ゆっくりと大きく動かすことが重要
→ 関節や腱に負担がかかるのを防ぎます
- 疼痛がある場合は即中止し、専門職に相談
→ 運動の継続可否を見極めることが必要です
- 動作中に前腕が浮いたり、他の関節が代償動作をしていないか確認
→ 肘や肩が動いてしまうと正しい運動にならない場合があります
- 可動域に制限がある場合は、その範囲内で行う
→ 無理をせず、少しずつ動かすことを優先しましょう
適切なフォームと頻度を守ることで、安全に機能維持を目指すことができる運動として活用できます。
まとめ|手関節の柔軟な動きが、日常動作を支える力になる
手関節の掌屈・背屈運動は、日常生活での「使う手」を育てるための基本的なアプローチです。
筋肉や関節の働きを無理のない範囲で引き出すことで、将来的な動作の安定や再発予防にもつながる可能性があります。
今回ご紹介した素材は、視覚的にわかりやすく、継続しやすい設計となっており、臨床現場や在宅支援、リハビリ初期〜中期の訓練まで幅広く対応可能です。

.jpg)