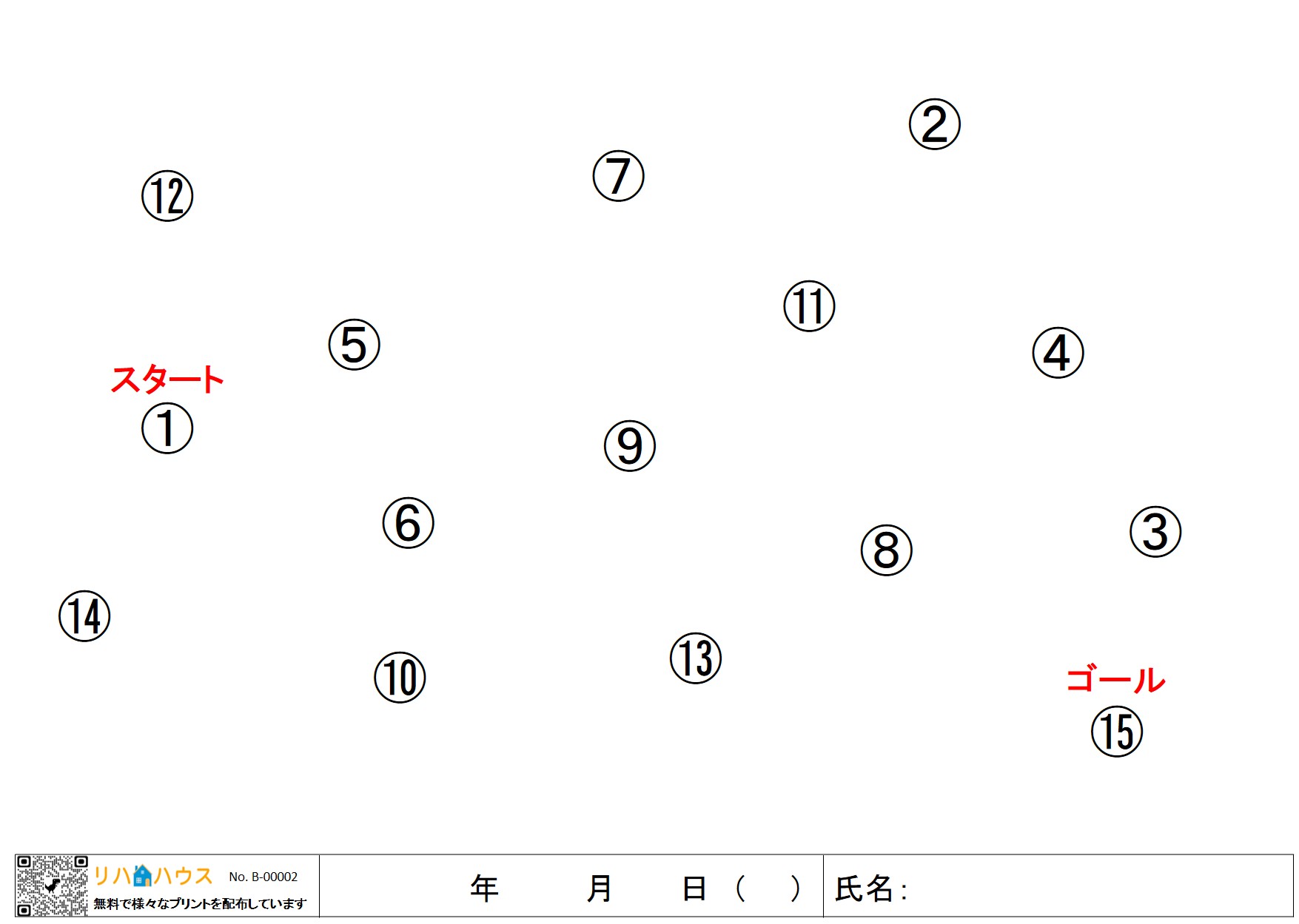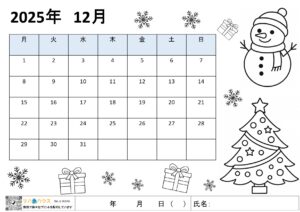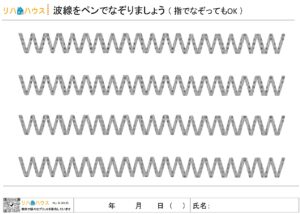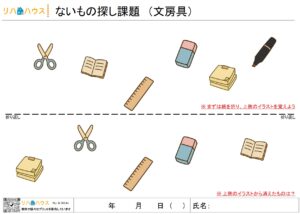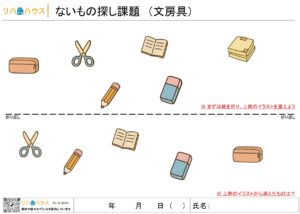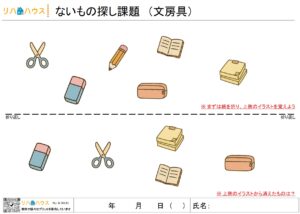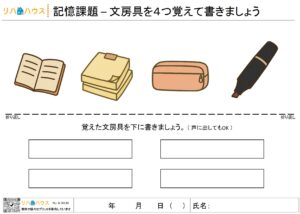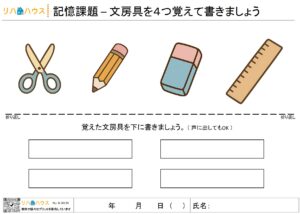このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。
はじめに|注意機能に働きかけるトレーニング素材「TMTプリント」第2弾
高次脳機能障害や注意障害のある方に対するリハビリテーションでは、認知機能のなかでも特に注意力・視覚探索・順序処理といった能力へのアプローチが重要視されます。
今回は、これらの機能訓練を紙面上で簡便に行えるTMT(Trail Making Test)形式のプリント素材・第2弾をご紹介します。
第1弾に引き続き、①~⑮の数字を順番に線でつなぐ一筆書き課題で構成されており、注意の持続や遂行機能の活性化を促します。
当プリントは、無料でダウンロード可能な自主トレーニング用素材です。臨床現場はもちろん、自宅でのリハビリやご家族の支援ツールとしてもご活用いただけます。
※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。
内容と目的|TMT課題がリハビリに与える機能的意義とは?
● TMTとは何か?
Trail Making Test(TMT)は、認知機能の多面的な側面――特に注意の持続、視覚探索能力、処理速度、遂行機能などを評価・訓練するために用いられる神経心理学的課題です。
本プリントはその中でも「TMT-A」型に該当し、①~⑮の数字を順に追って一筆書きでつなぐことで、以下の認知処理を誘発します。
| 誘発される機能 | 意図されるリハビリ的効果 |
|---|---|
| 視覚的探索 | 空間認知・注意の配分 |
| 数字の順序処理 | 前頭前野の機能強化 |
| 持続的注意 | 集中力・作業維持力 |
| ペン操作と制御 | 微細運動と実行力の訓練 |
● 第2弾のねらい
本記事で紹介する「その②」では、数字の配置がより広範囲に、ややランダム性を増した構成となっており、TMTに慣れてきた方や、認知負荷を少し高めたいケースに適しています。
運動方法と活用方法|紙面一枚で行える認知トレーニングの手順
● 実施方法
- プリントをA4サイズで印刷します。
- 用紙にランダムに配置された①~⑮を確認します。
- ①→②→③…と順番に、線を引いてつなぎます。
- ペンを紙から離さず、一筆書きでゴールまで進めます。
- 所要時間やエラー数を記録すると評価にも活用できます。
● 活用シーンの具体例
- 外来リハビリでの課題設定
- 通所リハ・デイケアでの個別対応
- ご家族による在宅支援
- TMT-A習熟後の発展課題として
● 応用ポイント
- タイム測定による評価
記録を残すことで進捗確認が可能です。
- 難易度調整
次回にTMT-B形式(数字と文字の交互)に進めるなど、段階的支援が可能です。
- 色分けによる視覚支援
高齢者や注意が散漫な方には、数字ごとに色のグループ分けを行うことで認識支援につながります。
注意点と安全への配慮|安心して取り組むためのポイント
● 課題実施時の配慮事項
- 疲労時は避ける
集中力を要する課題のため、体調が安定している時間帯を選びましょう。
- 失敗を責めない
うまくいかなかった場合でも、試行プロセスを評価の対象としてください。
- 補助が必要な場合の対応
文字の視認が困難な場合は、文字サイズを拡大して印刷するなど、視覚支援を行ってください。
● 医療専門職による活用の視点
- TMTの実施を通じて注意機能・遂行機能の現状評価が可能です。
- 作業療法士や言語聴覚士による観察記録との併用で、より高精度な支援計画の策定に役立ちます。
まとめ|TMT課題で注意と実行力の再構築を支援する
本記事でご紹介した【TMTプリントその②】は、認知リハビリにおける「注意・順序性・視覚的探索」のトレーニングに最適な素材です。
紙面一枚で完結するため、準備に手間がかからず、あらゆるリハビリ環境に柔軟に対応可能です。
また、ダウンロード形式のため、継続的な使用や評価にも適しており、患者様本人・ご家族・医療スタッフそれぞれが一貫した関わりを持つ支援ツールとしてもご利用いただけます。
次回以降も、段階的な難易度調整が可能なTMTプリントシリーズを公開予定です。ぜひ今後の臨床にご活用ください。